クロス取引を始めたいと思っていても、どれだけ費用がかかるのか分からないって人のために、細かく分解していきます。クロス取引は、現物の買いと信用の売りを権利付き最終日に同時に行う前提としてしています。
費用
取引手数料
まずは、取引手数料です。取引手数料は、証券会社ごとに異なりますが、一番少ないところでは、無料です。SBI証券や楽天証券が無料となってます。このブログでは、費用がないものとしています。
貸株料
2つ目は、貸株料です。信用取引をすると貸株料がかかってきます。これも証券会社により異なりますが、制度信用売りだと概ね年率1%程度です。一般信用売りだと1%~4%となります。日数は権利確定日とその翌日が平日だと最低の2日間となります。逆日歩の日数にプラス1日と考えれば大丈夫です。これは費用が事前に確定します。制度信用売りのイメージでは1日あたり100万で50円ちょっと超えるなくらいです。
配当落調整金
意外と知られていないのが、配当落調整金です。これは配当の支払いがあった時に費用として追加されるもので、制度信用売りでは、配当の84.685%です。一般信用売りでは、配当の100%となります。これは費用が確定するものではありませんが、現物での配当があるため、マイナスになることはありません。
逆日歩
クロス取引をする上で一番ネックになるのが逆日歩です。
逆日歩には最大値があり、1日1株あたり1.25円または株価の100分の1に0.2を乗じた額の大きい方となります。また、適用倍率というものがあり、権利付き最終日だと全銘柄4倍、注意喚起だと8倍、停止銘柄の一部で10倍となります。
逆日歩の最大値は計算で算出されますが、逆日歩の額は日証金が大株主に入札を行い、その応札額で決定されます。
逆日歩は、応札されるまで金額がわからないので、大きなリスクとして見られることも多いですが、銘柄の時価総額、株主構成、過去の逆日歩推移、株不足の程度などからあらかじめリスク評価することができます。このブログではこのリスク評価をブログの肝として情報発信しています。
収入
株主優待
収入の一つ目は、株主優待です。クロス取引は、基本的に株主優待を得るために行います。株主優待で優待利回り10%を超えるものもあります。例えば、クロスできる銘柄として楽天(4755)では、月30Gの通話SIMが1年間無料になります。これは、楽天モバイルで考えると、2,178円×12か月で26,136円の優待価値で、株価は900円程度なので利回りは、約30%にもなります。
配当
収入の二つ目は、配当です。一般信用では、配当の100%が配当落調整金として同額が費用になるため、利益は出ませんが、制度信用では、配当の84.685%が配当落調整金となるため、15.315%が利益となります。配当利回りが10%を超えるような銘柄では、株主優待がなくても利回り1%を超えるようなこともあります。
ちなみにですが、逆日歩は予定配当の15%程度で設定されることが非常によくありますが、配当による差益を得られないようにするためだと思われます。
利益
一般信用取引の場合
収入:株主優待
費用:貸株料
利益:株主優待 ー 貸株料
株主優待も貸株料もあらかじめ分かるため、簡単に利益が計算できます。ただし、一般信用在庫はすぐになくなったりするので、欲しいと思ったときには取得できないことが多いです。
制度信用取引の場合
収入:株主優待、配当
費用:貸株料、配当落調整金(配当の84.685%)、逆日歩
利益:株主優待 + 配当(15.315%) - 貸株料 - 逆日歩
配当落調整金は配当の84.685%のため先に差し引きしてます。こうして分解すると、そんなに難しいものではありません。費用が読めない逆日歩だけリスク管理をすれば、利益の安定化が図れます。

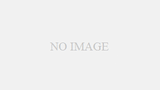
コメント